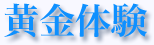私が鍵盤楽器と作曲を始めたのは高校生になってからです。家にピアノが置いてあったわけではありません。そっちの道に進んだわけでもありません。でも、どういういきさつだったのかは覚えていないのですが、カシオトーンを買ったんですよ。
当然、譜面は読めません。
好きなあのコから「いっしょにやろうよ!」なんて話を持ちかけられたわけでもありません。
人生は、そうそうゲームや漫画のように展開しませんからね(笑)。
さて、このカシオトーン。
いじったことがある方はご存知かもしれませんが、あれには自動伴奏機能がついておりまして、「ロック」とか「ポップス」などのジャンルを選ぶと、それっぽいフレーズで伴奏が流れます。で、さらに設定を変えると、左指で鍵盤を一つ押さえるだけで、伴奏がそのコード(和音)に変わります。メジャー、マイナー、セブンス、マイナーセブンスの4種類だったかな。
私は「FINAL FANTASY IV」のスコア(楽譜)を買ってきたんですよ。そのスコアを見ながら、そのカシオトーンでコードを「一本指奏法」で押さえていくと、なんと伴奏がゲームで流れていたあの曲っぽい雰囲気になるじゃありませんか!
感動です。
歌謡曲のコード譜なんかも買ってきて、毎日コードを押さえまくっていました。
そんな青春のある日のこと。諏訪部少年は、コードに一定の法則があることに気づきました。このコードの後には、このコードがくる。ここでこのコードが入っていて、あのコードにつながると曲がひと段落する、などなど。
がむしゃらにやっていくうちに、こうやって曲ができていて、こうやって曲を作っていくのだな、ということを学んだのです。
でっかい感動手に入れろ! です。
まるで世界の秘密を知ったかのような気持ちになりました。
その後、私は前述した「FINAL FANTASY IV」のスコアを弾くよりも、そのコード進行を使って「作曲」することが楽しくなってきました。そのあたりが今の源流ということになります。
勉強っていうのは、こういうことですよね。
0019/06/27
0019/06/26
時のある間に花を摘め。
Forgotten Sagaのなかで、ジュノはそんなもの枯れるだけじゃないかと言い放ちますが、草花を眺めて暮らす余裕は常に持ちたいものです。ストレス社会にいるとなかなか難しいものですけどね。
梅雨まっしぐら。
この時期の大御所といえば、紫陽花です。モコモコ。
咲き始めから終わりまでで少しずつ色が変化していきますが、土壌のペーハー濃度なんかでも変わるそうです。
そういえば昔、父親が紫陽花の一群のなかで一箇所だけ色が違う花があったときに「この下には死体があるよ、へへへ」と子供騙しをかましてきたことがありました。当時、子どもだったので、ストレートに騙されていたのは言うまでもありませんよ?
ところで紫陽花という漢字。
白居易が別の花につけた漢字を、平安時代の日本の学者が間違って当ててしまったのだそうです。
間違ってるけどそのままでいいや――そういうことって割とありますよね。
梅雨まっしぐら。
この時期の大御所といえば、紫陽花です。モコモコ。
咲き始めから終わりまでで少しずつ色が変化していきますが、土壌のペーハー濃度なんかでも変わるそうです。
そういえば昔、父親が紫陽花の一群のなかで一箇所だけ色が違う花があったときに「この下には死体があるよ、へへへ」と子供騙しをかましてきたことがありました。当時、子どもだったので、ストレートに騙されていたのは言うまでもありませんよ?
ところで紫陽花という漢字。
白居易が別の花につけた漢字を、平安時代の日本の学者が間違って当ててしまったのだそうです。
間違ってるけどそのままでいいや――そういうことって割とありますよね。
0019/06/05
音楽の楽しさをありがとう
羽田健太郎さんが死去したとのことです。
近年は「題名のない音楽会21」の司会を務められ、軽やかにピアノを弾く姿が印象的でした。
ところで、羽田健太郎さんといえば、ファミコン版の『ウィザードリィ』の音楽が(ゲームファンの中では)有名ですね。ウィザードリィといえば、当時、ソフトのパッケージに「このソフトは難しいから、小学校高学年以上の人がやってね!」みたいなニュアンスの注意書きがあることに衝撃を受けました。まぁ、内容はそれ以上に衝撃的で、何度も壁に閉じこめられましたけど(笑)。
また、坂本と氏についての話をしたところ、「タモリの音楽は世界だ!」に出ていたことを思い出しました。
あの番組は私も大好きでして、毎週楽しみに見ていました。特に、音楽当てクイズみたいなコーナーでは、MacとMIDI音源を使った早回しクイズみたいなノリでして、電子音楽に興味を持ったきっかけのひとつでもあります。
たしか、番組の最後にクイズがでて、プレゼントでMacがもらえるということで、必死にはがきを出していた気がします。結局、Macは当たりませんでしたけどね。
そんな風に広く音楽の楽しさを教えてくれた氏ですが、年齢的にはまだまだこれからの活躍が期待される方でした。
謹んでご冥福をお祈りします。
近年は「題名のない音楽会21」の司会を務められ、軽やかにピアノを弾く姿が印象的でした。
ところで、羽田健太郎さんといえば、ファミコン版の『ウィザードリィ』の音楽が(ゲームファンの中では)有名ですね。ウィザードリィといえば、当時、ソフトのパッケージに「このソフトは難しいから、小学校高学年以上の人がやってね!」みたいなニュアンスの注意書きがあることに衝撃を受けました。まぁ、内容はそれ以上に衝撃的で、何度も壁に閉じこめられましたけど(笑)。
また、坂本と氏についての話をしたところ、「タモリの音楽は世界だ!」に出ていたことを思い出しました。
あの番組は私も大好きでして、毎週楽しみに見ていました。特に、音楽当てクイズみたいなコーナーでは、MacとMIDI音源を使った早回しクイズみたいなノリでして、電子音楽に興味を持ったきっかけのひとつでもあります。
たしか、番組の最後にクイズがでて、プレゼントでMacがもらえるということで、必死にはがきを出していた気がします。結局、Macは当たりませんでしたけどね。
そんな風に広く音楽の楽しさを教えてくれた氏ですが、年齢的にはまだまだこれからの活躍が期待される方でした。
謹んでご冥福をお祈りします。
0019/06/03
G!
サイボーグじいちゃんGみたいなノリですが、そういえば製作日誌とか言っていたわりにはあまり製作の話はしていません。
といっても、製作の大部分は諏訪部の作業なので、そのへんはあまり気にせずスルー。
この日誌、G・エクスペリエンス。
おおむね、ゴールドだと思われるでしょうが、実はゲームとかけているわけです。だから、ゲームが関係していればなんでもいいだろう的な打算的な趣旨がそこにはあります。
諏訪部から聞いたところによると、次作の製作状況としては骨格部分に着手しつつも、音楽のメインテーマなどは出来上がっているらしいですよ。
次作でリューネたちも登場するといえば、Forgotten Sagaにも、すこぶるチョイ役で登場していました。登場するのは印象的なシーンなのですが、もしかしたら気づかずスルーだった人もいるかもしれません。いわゆるお遊び的なニュアンスでした。
ですが次作では、もうちょっと大々的に登場します。
映画の続編とかでもよくありますよね、旧作の人物が意外な登場をするパターンや続編自体がわりと意外な設定で始まるパターン。
そんなような感じになるのではないかと思います。
といっても、製作の大部分は諏訪部の作業なので、そのへんはあまり気にせずスルー。
この日誌、G・エクスペリエンス。
おおむね、ゴールドだと思われるでしょうが、実はゲームとかけているわけです。だから、ゲームが関係していればなんでもいいだろう的な打算的な趣旨がそこにはあります。
諏訪部から聞いたところによると、次作の製作状況としては骨格部分に着手しつつも、音楽のメインテーマなどは出来上がっているらしいですよ。
次作でリューネたちも登場するといえば、Forgotten Sagaにも、すこぶるチョイ役で登場していました。登場するのは印象的なシーンなのですが、もしかしたら気づかずスルーだった人もいるかもしれません。いわゆるお遊び的なニュアンスでした。
ですが次作では、もうちょっと大々的に登場します。
映画の続編とかでもよくありますよね、旧作の人物が意外な登場をするパターンや続編自体がわりと意外な設定で始まるパターン。
そんなような感じになるのではないかと思います。
0019/05/28
肉のパイ
創刊号だけ特別価格でおなじみ(?)のアレ。今回はピーターラビットということで、思わず買ってしまいました。イラストのタッチが優しい感じでとても良いです。物語も載っていたのですが、そこでピーターの父親が「肉のパイ」にされた、と母親がさらっと言っているところが、なかなかシュールでしたけど。
しかしまぁ、作者がいなくなってしまっても、作品も、そのキャラクターも愛され続けているということは、なんだか素敵なことだと思います。作品を作るうえで、自分の個性や味を出していくことは大事なんですけど、なんといっても誰かに支持されないことには淋しい気もするのですよ。だから、そういう部分も大事なのかな、と思ってがんばっていきたいですね。
ちなみに。
坂本から聞きましたけど、次回作はリューネも出るそうですよ! ということは、もちろんあのキャラクターも……!?
しかしまぁ、作者がいなくなってしまっても、作品も、そのキャラクターも愛され続けているということは、なんだか素敵なことだと思います。作品を作るうえで、自分の個性や味を出していくことは大事なんですけど、なんといっても誰かに支持されないことには淋しい気もするのですよ。だから、そういう部分も大事なのかな、と思ってがんばっていきたいですね。
ちなみに。
坂本から聞きましたけど、次回作はリューネも出るそうですよ! ということは、もちろんあのキャラクターも……!?
0019/05/22
言葉はいらない?
先日、樹木の鬱蒼と茂る公園を散策中に、
ピロピロポロポロピー♪
という抑揚のあるメロディが頭上から聞こえ、ん? と仰いでみたところ、そこにおわすはジュウシマツ。
ポロッピピピピロポロピー♪
思いのほか美声。
しばらく見ていたら飛び去ってしまいましたが、思わぬ路上ライブに得した気分です。
なにを言っているのかわからないけれど、なんとなく楽しい気持ちになりました。きっとそのジュウシマツもそんな気分だったに違いないと恣意的に解釈しました。
Fogotten Sagaのなかに、もこもこアイス(このネーミングもう少しなんとかならなかったんでしょうか)というトーン(精霊)が出てきます。そいつは「めぇめぇ」しか話せないのですが、アストリアは言葉ではなくそこに込められた想いを感じることで、主張を受け入れることができます。
気持ちでカバー。
心が通じ合うとき、そこに言葉はないのかもしれませんね。
ピロピロポロポロピー♪
という抑揚のあるメロディが頭上から聞こえ、ん? と仰いでみたところ、そこにおわすはジュウシマツ。
ポロッピピピピロポロピー♪
思いのほか美声。
しばらく見ていたら飛び去ってしまいましたが、思わぬ路上ライブに得した気分です。
なにを言っているのかわからないけれど、なんとなく楽しい気持ちになりました。きっとそのジュウシマツもそんな気分だったに違いないと恣意的に解釈しました。
Fogotten Sagaのなかに、もこもこアイス(このネーミングもう少しなんとかならなかったんでしょうか)というトーン(精霊)が出てきます。そいつは「めぇめぇ」しか話せないのですが、アストリアは言葉ではなくそこに込められた想いを感じることで、主張を受け入れることができます。
気持ちでカバー。
心が通じ合うとき、そこに言葉はないのかもしれませんね。
0019/05/12
テストでも問題をよく読んでから
先日、あるカメラを買ったんですよ。
バーバーと撮りまくって、ワクワクが押しよせながらフィルムを現像に出しました。しかし、現像から上がってきた写真は、すべてピンボケ(笑)。さすがに、全部が全部ピンボケというのはあまりにおかしいので、機器の故障を疑いました。
とりあえず、そのカメラとその説明書を見ていたら、どうもレンズがしっかりとはまっていなかったらしい。
説明書には、「カチッと音がするまでレンズを回して取り付けます」と書いてあった。そういえば、どうもレンズがユルユルな感じだとは思っていたのですけどね。いつもの調子で適当にやっていたら、思わぬ盲点があったわけです。
やはり、説明書はちゃんと読まなければダメだなぁ、と感じた出来事でした。
そんな説明書。もちろん、ゲームにも付いてきます。
それは、どのボタンを押せばどうなる、という説明でしたが、RPGにおいては、「Aボタン=決定」「Bボタン=キャンセル」という暗黙の了解があります。そのため、たいていのRPGは説明書を読まなくても、いきなりゲームを始められます(武器や魔法の効果や、ゲームごとの細かい部分は多々ありますが)。
MEET INVADEのゲームは、「RPGツクール」というツールで作っていますが、ゲーム中の操作はきわめてシンプル。戦闘シーンも凝った自作物ではなく、普通のものであるし、フィールドマップがあって、街があって、ごく普通のRPGと同じです。小難しいことを考えずにとりあえずプレイしてね! というスタイルを目指しています。
そういえば、特に説明はしていなかったのですが、「Return to Farland」では、マップのオブジェクト(壺や壁の物など)を調べることでもアイテムが手にはいることがあります。宝箱以外にもアイテムが手に入るというのは、どうも気づきにくい部分だったかもしれません(Forgotten Sagaには、そういうケースはほとんどありません)。
特によくいただく質問に「ハー・グローブはどこにあるのですか?」というものがありますが、これは時期もあるうえ、壁のオブジェクトを調べることで手にはいるので、ある意味では意地悪な感じだったかもしれませんね。
バーバーと撮りまくって、ワクワクが押しよせながらフィルムを現像に出しました。しかし、現像から上がってきた写真は、すべてピンボケ(笑)。さすがに、全部が全部ピンボケというのはあまりにおかしいので、機器の故障を疑いました。
とりあえず、そのカメラとその説明書を見ていたら、どうもレンズがしっかりとはまっていなかったらしい。
説明書には、「カチッと音がするまでレンズを回して取り付けます」と書いてあった。そういえば、どうもレンズがユルユルな感じだとは思っていたのですけどね。いつもの調子で適当にやっていたら、思わぬ盲点があったわけです。
やはり、説明書はちゃんと読まなければダメだなぁ、と感じた出来事でした。
そんな説明書。もちろん、ゲームにも付いてきます。
それは、どのボタンを押せばどうなる、という説明でしたが、RPGにおいては、「Aボタン=決定」「Bボタン=キャンセル」という暗黙の了解があります。そのため、たいていのRPGは説明書を読まなくても、いきなりゲームを始められます(武器や魔法の効果や、ゲームごとの細かい部分は多々ありますが)。
MEET INVADEのゲームは、「RPGツクール」というツールで作っていますが、ゲーム中の操作はきわめてシンプル。戦闘シーンも凝った自作物ではなく、普通のものであるし、フィールドマップがあって、街があって、ごく普通のRPGと同じです。小難しいことを考えずにとりあえずプレイしてね! というスタイルを目指しています。
そういえば、特に説明はしていなかったのですが、「Return to Farland」では、マップのオブジェクト(壺や壁の物など)を調べることでもアイテムが手にはいることがあります。宝箱以外にもアイテムが手に入るというのは、どうも気づきにくい部分だったかもしれません(Forgotten Sagaには、そういうケースはほとんどありません)。
特によくいただく質問に「ハー・グローブはどこにあるのですか?」というものがありますが、これは時期もあるうえ、壁のオブジェクトを調べることで手にはいるので、ある意味では意地悪な感じだったかもしれませんね。
0019/04/30
永遠の記録。
すでに何度も書いていることですが、Return to FarlandやForgotten Sagaでは名前のない人たちにもなるべく設定を用意しました。人類の歴史のなかには、名前のない人のほうがずっと大勢いるからです。その姿勢は、次作でも貫かれるのではないかと思います。
ところで、MEET INVADEの拠点がある首都圏の片隅は、大河ドラマのおかげか最近少しスポットを浴びたりしています。
そんなわけで先日、とても晴れていたので、旧跡を訪ねてきました。武田氏に縁のある古城跡です。
まるで真夏のような気候と、むっとくる草いきれにちょっと辟易しましたが、そのぶんなぜか落ち着きました。
旧跡で佇んでいると、ずっと昔にもそこに人がいたことや、今そんなところに自分が立っていることを少し不思議に思ったりもします。
たとえば千年もまえに、こんなところに人が大勢いたり、だれかと攻防を繰り広げていたり、また隠れて恋をしたりしていたのかと思うと、歴史が文字や記号じゃない生身のものとして感じられるような瞬間があったりもするわけです。
風が過ぎ去るように刹那の淡い夢です。
ところで、MEET INVADEの拠点がある首都圏の片隅は、大河ドラマのおかげか最近少しスポットを浴びたりしています。
そんなわけで先日、とても晴れていたので、旧跡を訪ねてきました。武田氏に縁のある古城跡です。
まるで真夏のような気候と、むっとくる草いきれにちょっと辟易しましたが、そのぶんなぜか落ち着きました。
旧跡で佇んでいると、ずっと昔にもそこに人がいたことや、今そんなところに自分が立っていることを少し不思議に思ったりもします。
たとえば千年もまえに、こんなところに人が大勢いたり、だれかと攻防を繰り広げていたり、また隠れて恋をしたりしていたのかと思うと、歴史が文字や記号じゃない生身のものとして感じられるような瞬間があったりもするわけです。
風が過ぎ去るように刹那の淡い夢です。
0019/04/17
ウサギとカメ
だいぶ間隔が空いてしまいましたが、諏訪部です。
新年度も始まり、そろそろ新しい生活にも慣れてきた頃でしょうか。もう少しすれば、今度は五月病なんていう話も出てきたりするんですかね。ま、暗闇に入ってしまったら、焦らず慌てずが基本です。これは、実際に我々が暗いところに入ってしまってもそうですからね。心の暗闇も、同じようなもんです。
さて、たまには制作中のゲームについてのお話をします。
あまり時間が割けないということもあり、亀のスピードなんですが、毎日一歩は歩くようにしています。歩いていればゴールにたどり着けると信じていますので。
で、次回作。世界観は「Return to Farland」や「Forgotten Saga」を引き継いでいます。つまり、ファーランドが舞台のお話になります。いつの時代のファーランドかはまだ言えないのですが、とにかくそんなわけですので、皆さんよくご存じのキャラクターも登場します。
まだまだ開発状況なんて言えるほど進んでいませんが、首をキリンさんにしてお待ちいただければ幸いです。
余談ですが。
先日、株式会社英知出版社より発売されました「ゲーム業界激震!次世代フリーゲームの殿堂」にて、「Return to Farland」が紹介されました。オールフルカラーで、他にも様々なゲームが紹介されています。詳細はおって報告しますが、よろしかったらご覧になってみてください。
新年度も始まり、そろそろ新しい生活にも慣れてきた頃でしょうか。もう少しすれば、今度は五月病なんていう話も出てきたりするんですかね。ま、暗闇に入ってしまったら、焦らず慌てずが基本です。これは、実際に我々が暗いところに入ってしまってもそうですからね。心の暗闇も、同じようなもんです。
さて、たまには制作中のゲームについてのお話をします。
あまり時間が割けないということもあり、亀のスピードなんですが、毎日一歩は歩くようにしています。歩いていればゴールにたどり着けると信じていますので。
で、次回作。世界観は「Return to Farland」や「Forgotten Saga」を引き継いでいます。つまり、ファーランドが舞台のお話になります。いつの時代のファーランドかはまだ言えないのですが、とにかくそんなわけですので、皆さんよくご存じのキャラクターも登場します。
まだまだ開発状況なんて言えるほど進んでいませんが、首をキリンさんにしてお待ちいただければ幸いです。
余談ですが。
先日、株式会社英知出版社より発売されました「ゲーム業界激震!次世代フリーゲームの殿堂」にて、「Return to Farland」が紹介されました。オールフルカラーで、他にも様々なゲームが紹介されています。詳細はおって報告しますが、よろしかったらご覧になってみてください。
0019/04/02
浅き夢見し。
花より鼻で春を感じる人も多いでしょうか。
学生時代、恐ろしいくらい花粉症で鼻づまりは日本海溝ばりだったのですが、なぜか最近はのどが少しイガイガする程度で、その頃の名残はあまりありません。
花粉症は一度なると、一生治らないと聞いたのですが不思議なものです。
閑話休題。
暖かくなってくると、なんとなく気だるいような空気感に、ちょっぴりセンチになったりもします。
春が新しい季節という感覚は昔からあまりなく、厭世的な人間だったためむしろ、春は少し憂鬱だったという記憶があります。変化を嫌う人間の特徴ですね。
今は日々それなりに忙しいので昔ほど感傷的ではなくなりましたが、それでもふとした瞬間に、春が憂鬱だった頃を思いだし、懐かしいような淋しいような気持ちになることがあります。桜をみるといろいろなことを思いだす――そういえば、そういう俳句がありましたね。
近年は、桜をみていると、人生であと何回この花をみるのだろうと、未来について思いふけったりすることもあります。
桜をまえにすると、人生の岐路に立ったような気分になることがあるのです。
過去も未来も小さなことなのかもしれませんが、切ないとはそういうことを言うのかもしれないとか思ったりします。
桜を見たときの気持ちを言葉にするのはとても難しいことに気づきました。
学生時代、恐ろしいくらい花粉症で鼻づまりは日本海溝ばりだったのですが、なぜか最近はのどが少しイガイガする程度で、その頃の名残はあまりありません。
花粉症は一度なると、一生治らないと聞いたのですが不思議なものです。
閑話休題。
暖かくなってくると、なんとなく気だるいような空気感に、ちょっぴりセンチになったりもします。
春が新しい季節という感覚は昔からあまりなく、厭世的な人間だったためむしろ、春は少し憂鬱だったという記憶があります。変化を嫌う人間の特徴ですね。
今は日々それなりに忙しいので昔ほど感傷的ではなくなりましたが、それでもふとした瞬間に、春が憂鬱だった頃を思いだし、懐かしいような淋しいような気持ちになることがあります。桜をみるといろいろなことを思いだす――そういえば、そういう俳句がありましたね。
近年は、桜をみていると、人生であと何回この花をみるのだろうと、未来について思いふけったりすることもあります。
桜をまえにすると、人生の岐路に立ったような気分になることがあるのです。
過去も未来も小さなことなのかもしれませんが、切ないとはそういうことを言うのかもしれないとか思ったりします。
桜を見たときの気持ちを言葉にするのはとても難しいことに気づきました。
登録:
投稿 (Atom)